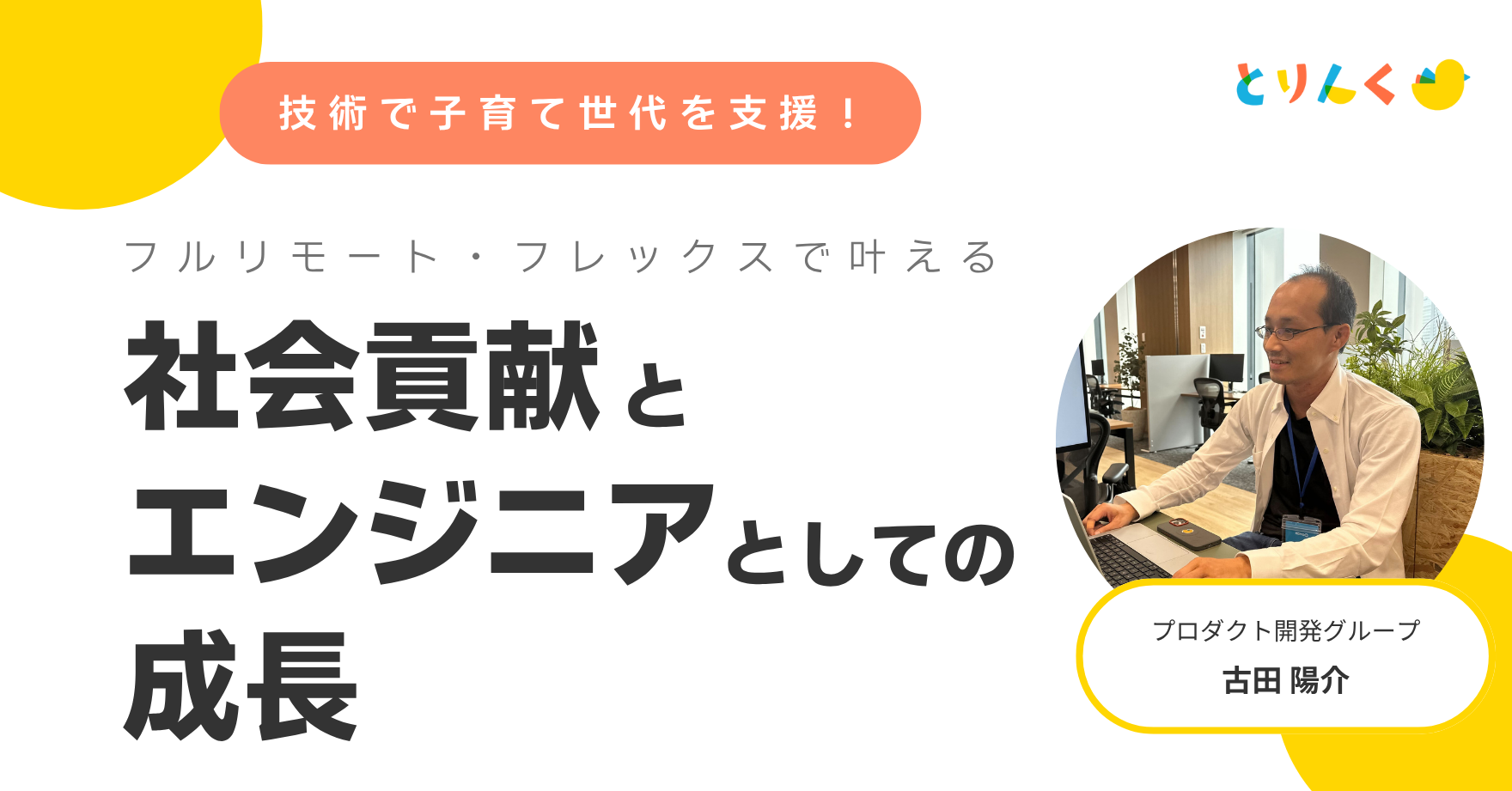
日々、保育園でどんなふうに過ごしているのか。まだ言葉の少ない幼い子どもの“いま”を、保護者は想像するしかありません。そんな“見えない日常”をテクノロジーの力で“見える”ようにしたのが、株式会社とりんくです。
保育士の業務を支え、保護者と子どもをつなぐ。その開発の裏側には、自らも子育て中のエンジニア・古田さんの思いがありました。今回は自らの育児経験も重ねながら、エンジニアとして“社会に効く技術”を磨き続ける開発者としてのやりがいや、求める人物像について、お伺いしました。
※とりんくがコドモングループにジョインした背景はこちら
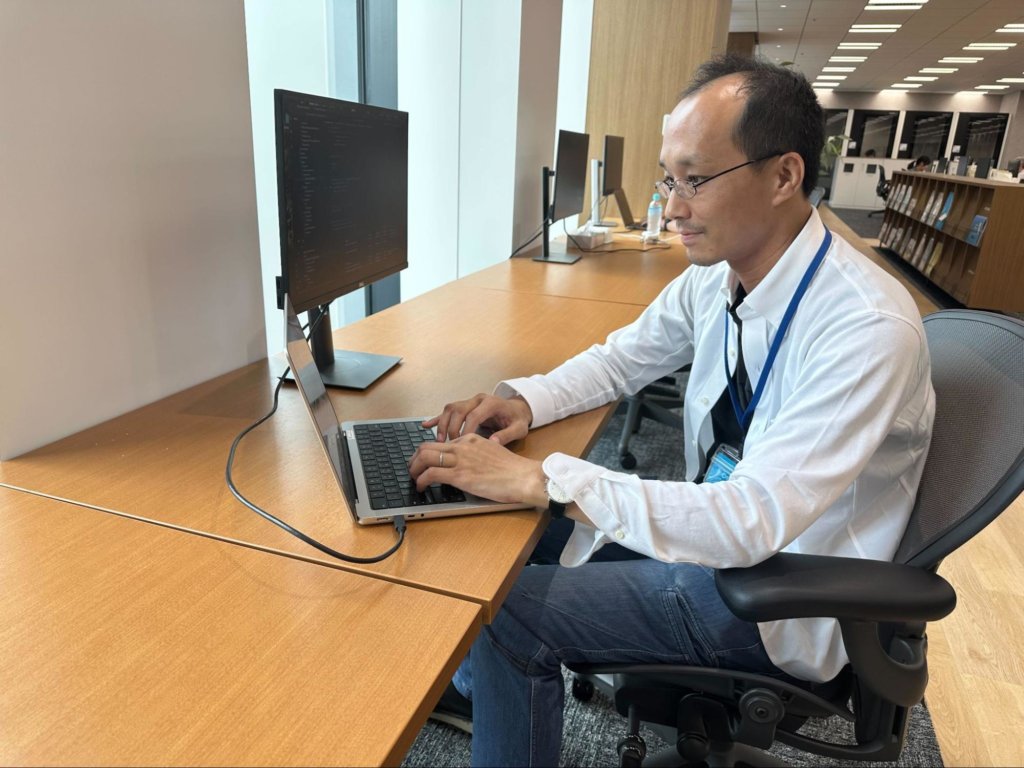
古田陽介 | プロダクト開発グループ(エンジニアリングマネージャー/テックリード)
新卒でサイバーエージェントに入社し、アメブロの基盤システム開発やリプレイス業務に従事。その後、LINE株式会社にてIoT系サービスのプラットフォーム開発をリード。エクサウィザーズに転職後、保育・教育施設向けAI写真サービス「とりんく」の立ち上げに関わる。保育現場への理解と高い技術力を掛け合わせ、ユーザー視点でのプロダクト改善に取り組んでいる。
子どもの「見えない日常」を「見える」ように
ーまずはじめに、株式会社とりんくのサービスについて教えていただけますか?
古田:私たちが提供する「とりんく」は、保育・教育施設向けのAI写真サービスです。
保育者の写真撮影をAIがサポートし、撮影された写真の中から保護者にとって価値のあるものをAIが選び、適切なタイミングで届けることが主な役割です。保育士さんの業務を軽減しながら、保護者が子どもの日常を“見える化”できるサービスです。
ー保育園に預けている保護者にとって、日中の子どもの様子って見えづらいですよね。
古田:そこが一番大きな課題だと思います。保護者としては「今日は保育園で何をしていたんだろう?」「どんな表情で過ごしていたんだろう?」と気になりますよね。もちろん、定期的にDVDが配られたり、写真の販売サービスがあったりはしますが、3ヶ月前の出来事がようやく手元に届くようなタイムラグがどうしてもあります。
ータイムリーではない、というのはやはり課題ですか?
古田:子どもって毎日違うんですよ。1週間で顔つきも、遊び方も変わっていきます。だからこそ、その日の出来事がその日のうちに届くというのは、親子のコミュニケーションにすごく価値があると思うんです。
たとえば夕食時に「今日、◯◯ちゃんと砂場で遊んだの?」と話しかけるだけでも、子どもはうれしいはず。保護者としても、“今日”の子どもをきちんと見てあげられている実感が湧くと思います。
ー技術的にそれを可能にしているのが、AIということですね。
古田:写真の中に写っている子どもを自動で識別し、保護者が喜ぶような“良い写真”を自動で選別するといった一連の処理を、AIが担っています。
私たちの目標は、保育士さんの負担を減らすことでもあるので、できるだけ自動化・省力化にも注力しています。
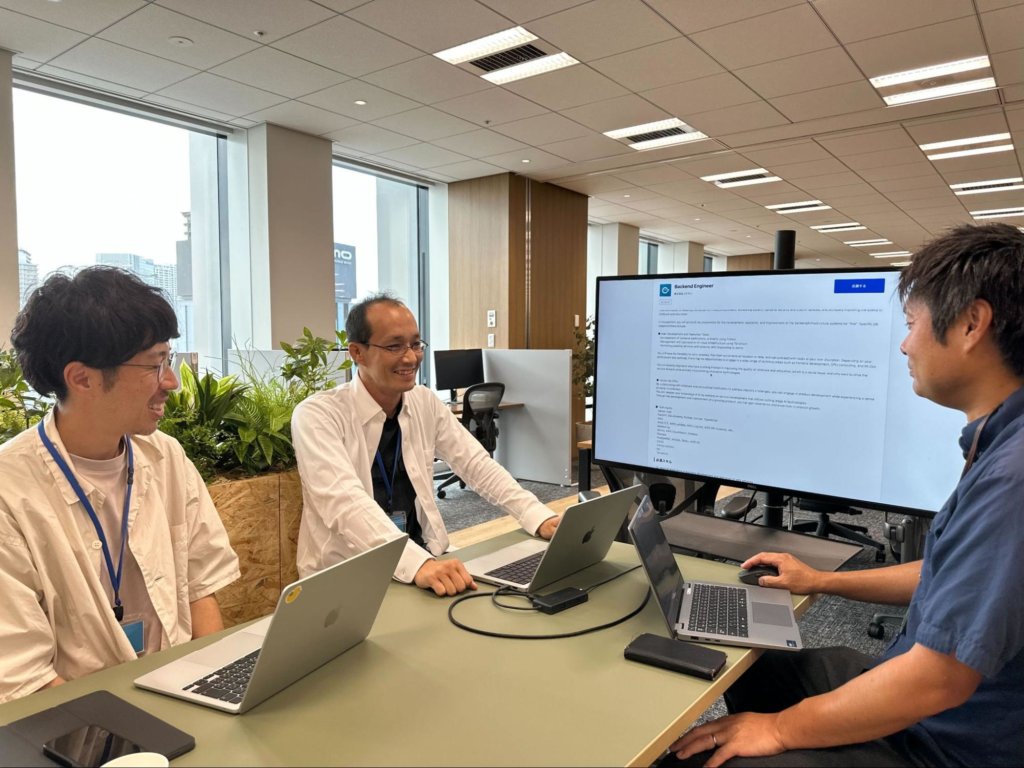
ー子どもの日常が見えるようになることで、保護者にはどんな変化がありますか?
古田:子どもをより一層、理解できるようになりますよね。小さな子どもは、まだ言語化がうまくできないので「今日は何してたの?」と聞いても返事がかえってこないことも多いはずです。しかし写真があれば「こういう遊びをしてたんだね」「この子と仲良くしてるんだね」と自然と会話が広がります。子どもの“今”に寄り添えるし、保育園と家庭の信頼も深まる。これは、保育の質を底上げすることにもつながると思っています。
ーすごく実感を伴ったお話ですね。古田さんご自身も、お子さんを保育園に預けていた経験がおありなんですよね?
古田:とりんくの開発を始めた頃、ちょうど子どもが生まれたタイミングでした。だから、自分が関わるサービスで「子どもと家庭の距離を縮める」ことができるのは、すごく嬉しかったし、取り組む意義を強く感じました。
ー保育とテクノロジーの接点に、ご自身の生活が重なったわけですね。
古田: はい。技術は、社会課題とつながってこそ意味があると思っています。 保育士さんの負担を減らしたい、保護者と子どもをもっとつなぎたい。 そうした想いを持って開発しているからこそ、ユーザーの声を聞いたときの喜びも大きいですし、エンジニアとしてのやりがいも強く感じます。
子ども専用に最適化された顔認識AI。“いい写真”を見極める技術
ー写真の選定や分類における技術的な仕組みを教えていただけますか?
古田:特徴的なのは「子ども専用に最適化された顔認識AI」を使っているという点です。顔認識そのものの技術は世の中に多く存在しますが、子どもの顔は、大人と比べて表情や顔の成長も著しくて、認識が難しいんです。私たちは子どもに特化した独自のAIモデルを開発しており、そのような問題に対応しています。
ー子どもの顔を正確に認識するには、それだけ高精度なAIが求められるんですね。
古田:さらに言うと、ただ識別するだけじゃなくて“いい写真かどうか”も判別しています。先生や保護者にとって意味のある写真、たとえば子どもが笑っている、集団で遊んでいる、活動の様子がしっかり写っているといった、フォトジェニックな写真を選ぶAIも搭載しています。
ー写真の良し悪しをAIが判断しているんですか?
古田:はい。過去に蓄積してきた、“いい写真”の傾向やデータをもとに、ディープラーニングでモデルを学習させています。つまり、保護者や先生に好まれる写真のパターンを、AIが理解して判別しているというわけです。この技術によって、ユーザーに届く写真の質も安定し、不要な画像をクラウドに保存する無駄も減らせるんです。
ー技術的にかなり高度なことをされているんですね。開発言語や構成についても伺ってもいいですか?
古田:バックエンドはPythonが中心で、写真の識別処理やデータ管理はFastAPIというPython製の軽量フレームワークを使っています。一方でフロントエンドはTypeScript+Vueなど、一般的なWebスタックです。写真を解析してタグ付けし、保護者に届ける一連の流れは、マイクロサービス化された各種機能を呼び出して実現されています。
ー画像解析や識別は、ユーザーの操作に応じて即時に行われるオンライン処理ですか?それとも非同期のバッチ処理でしょうか?
古田:基本的には非同期のバッチ処理で動いています。写真が一定量アップされたタイミングで、推論エンジンを呼び出して画像を識別・分類し、メタデータとともにデータベースに保存しています。
顔認識システムを社内で提供しているので「この写真の中には誰が写っているのか」「その人物である可能性(類似度)は何%か」といった情報もAPIで簡単に取得できるようになっています。
ー推論APIを内部で運用されているんですね。インフラ環境についても教えてください。
古田:現在はAWSのクラウドに完全移行しています。以前はオンプレミス環境でGPUサーバを稼働させていた時期もありましたが、今はクラウド一本化です。
とはいえ、今後も技術やプロダクトの変化に応じて、構成を柔軟に変えていける余地はあります。サーバーレスで済むところは済ませますし、GPUインスタンスを使用し、AIモデルの推論処理をしています。
ーインフラの構成にも柔軟さを持たせて運用されているとのことですが、現在の仕組みで、改善の余地を感じている点はありますか?
古田:バッチ処理にかかるコストが、今のフェーズでは少し重たくなってきたと感じています。サービス初期のニーズに最適化された構成は、運用や仕様変更を経た現在の姿と必ずしも合致していないところがあるんですよね。今後の運用を見据えて、アーキテクチャを見直していく必要があると思っています。
ーより理想的なアーキテクチャを目指していく中で、どのような改善が必要だと感じていますか?
古田:現在は、不具合が発生した際、どのソフトウェアコンポーネントで問題が起きているのかを正確にトレースするのが難しかったり、ログの取り方にまだ工夫の余地があったりします。運用面での課題が少しずつ積み上がってきている状況です。技術的負債に近い状態とも言えますが、裏を返せば「手を入れられる余白がたくさんある」ということでもあります。今後、新しく入ってくださるエンジニアの方が、インフラやアーキテクチャの再設計に興味を持っているなら、非常にやりがいのあるフェーズだと思います。既存の構成を一緒に見直して、よりシンプルで持続可能な仕組みにしていく、そんな取り組みをチームで進めていきたいです。
少数精鋭のチームでスピードと裁量を両立
ー開発チームの体制について教えていただけますか?
古田:現在は、正社員が3名、業務委託が1.5名の体制(2025年5月末現在)です。少人数ですが、その分意思決定のスピードは早いですし、一人ひとりの裁量も大きいですね。チーム全体で何をどう進めるか、細かくすり合わせながら開発をしています。
ータスクの管理や開発の進め方は、どういったスタイルでしょうか?
古田:アジャイル開発をベースにしています。JIRAを使ってチケット管理をしていて、スプリントプランニングを行いながら「今、何を優先すべきか」「誰がどこを担当するか」などを話し合っています。 大きな仕様変更を伴うような開発はプロダクトマネージャーが中心になってリードしてくれることが多いですし、 改善系の業務はエンジニア主導で自発的に進めていく、というバランスです。
ーチームが少人数であることのメリットはどう感じていますか?
古田:コミュニケーションが取りやすいことです。人数が増えると、それだけ情報共有の手間がかかるし、ちょっとしたズレも生じやすくなってきます。コミュニケーションコストが高いと、チャレンジングな実装なども行いにくくなってきてしまうため、今のような少数精鋭だと断然動きやすいと考えています。
よく「チームは2枚のピザで足りる人数がベスト」と言われることがありますよね。Amazonが実践している考え方ですが、私もその感覚に共感していて。今のチーム規模はまさにそのサイズ感で、必要なときにすぐ話し合えて、柔軟に意思決定ができる環境だと思います。
ーひとりあたりの守備範囲も広くなりそうですね。
古田:そうですね。担当する範囲は、広いと思います。ただ、それがネガティブに働いているというよりは「やれることが増える=成長できる」と考えているメンバーばかりです。「やってみたい」と前向きに関わってもらえる方には、すごく相性がいいと思います。
ー新しくジョインする方に期待することがあれば、教えてください。
古田:自分の意見を持っていて、責任を持って取り組める人と一緒に働きたいですね。「これはおかしい」「こうしたほうがいい」と思ったら、声に出してほしいです。 仕事だからなんとなくやるのではなく「自分がどうしたいか」を言葉にできる人だと、私自身もすごく刺激を受けますし、チームとしても成長できると感じています。

仕事の生産性を高める柔軟な働き方
ーフルリモート・フレックスを導入されていますが、働きやすさはいかがですか?
古田:とても働きやすいです。 私の持論ですが、仕事は時間を注ぎ込むことではなく、成果を出すことの方が重要だと思っています。 その点、リモートやフレックスは、家庭や個人の事情に合わせて働けるので、集中して取り組める。結果的に、成果も出しやすくなると感じています。
ー古田さんも、ご家庭を持ちながら働いていらっしゃるとのことでしたね。
古田: はい。一般的な出社パターンって、朝早く出て、夜遅く帰ってくるという生活スタイルで「子どもとまともに話す時間がない」という状況になりがちですよね。 しかし私の場合は、子どもたちと夕飯を一緒に食べて、夜も一緒に過ごせます。 本当にありがたいです。
ー家庭を大事にしながらも、プロフェッショナルな仕事ができると。
古田:その通りです。家庭をおろそかにして仕事に集中するというのは、僕にとっては本末転倒なんです。 どちらも大事にしたい。そのためにどう働くかを自分で設計できる環境が、この会社にはあります。 エンジニアの仕事は基本的にリモートで完結するものが多いですし、ツールを活用すれば、情報共有やタスク管理も問題ありません。
ー“無理せず成果を出せる”というのは、求職者にとっても魅力的に映りそうです。
古田: 働き方は、その人の人生そのものに影響すると思うんです。 だからこそ、チームとして「どうすれば最大のパフォーマンスが出せるか?」を一緒に考えていく姿勢が大事だと思っています。 今後入ってくださる方にも、家庭やプライベートを大切にしながら、エンジニアとして本気で取り組める環境を提供したいです。
ー一般的な企業では、階層的なキャリアパスがありますが、とりんくのキャリアに対する体制を教えてください。
古田: 今のところ階層的な構造はありません。 今後、組織が大きくなれば仕組みが整ってくることもあるかもしれませんが、今は非常にフラットです。
ー最後に、これからチームに加わる方に「ここで働く意義」をどんなふうに感じてほしいですか?
古田:私たちの仕事は、保育士さんの負担を減らす技術や、保護者と子どもをつなぐツールの開発です。このような社会的課題の解決は、大きなモチベーションになると思います。いずれ、子どもたちの成長や、家族のつながりに直結していくという実感を、ぜひ一緒に味わってほしいです。
あなたの技術が、日本の保育を変える力になる
株式会社とりんくは、保育という社会課題に対して、技術で向き合う少数精鋭のチームです。
エンジニアとしての専門性を発揮しながら、社会課題を解決する実感が得られる場所であり、「自分で考え、動く」姿勢も求められます。
チャレンジ精神を持っている人、自分のキャリアを自分で切り拓いていきたい人にとっては、間違いなくやりがいのある環境です。
これからも、私たちの取り組みを少しずつ発信していきます。お楽しみに。
その他にも対談記事などを掲載しておりますので、是非ご覧ください!
「保育AI」のあるべき姿とは? ~コドモン×とりんくが描く、保育と技術のあたらしい関係~https://www.codmon.com/column/ai_2/
「保育AI」のあるべき姿とは? 〜とりんくが考える、子どもの未来を広げるためにAI写真ができること〜https://www.codmon.com/column/ai_3/
とりんくのエンジニアの募集はこちら!
とりんく:バックエンドエンジニア / Backend Engineer
とりんく:シニアバックエンドエンジニア/ Backend Engineer
とりんく:画像AIエンジニア/Computer Vision Engineer
